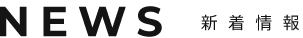坂口志文先生、そして奥様である坂口教子先生、ノーベル生理学・医学賞受賞おめでとうございます!
私にとっては、坂口先生は、畏れ多い大先輩であり、免疫学の師匠であり、また、会社の立ち上げに加わってからは、共に戦う同志、と思っています。
そんな身近な人がノーベル賞を受けられた…!毎年候補にあがっておられたとはいえ、実際にノーベル賞発表の中継で名前を聞いた時は、鳥肌が立ち、しばし絶句した後、「え?え?」「おお!」と、思わず声をあげました。
坂口志文先生と私は、治療戦略について意気投合して、2016年に坂口先生がレグセルを創業される際に、創業メンバーに加えていただきました。意気投合した内容は、「獲得免疫系の細胞そのものを使って、治療法を開発したい」という事です。坂口先生は制御性T細胞を使い、私はキラーT細胞を使って、「T細胞療法の会社」にしようという事でした。
その坂口先生がノーベル賞を受けられたということは、リバーセルにとっても、大変意義深いと言えます。リバーセルは、2019年にレグセルからの分社化という形で創業しましたが、対象疾患や開発フェーズが異なってきたため、身動きがつきやすいように円満に分社化したのであって、今も志は共有しており、「将来は共同事業を」という話はよくしています。
制御性T細胞の発見の意義について書きます。「自己寛容はどうやって成立するのか」は免疫学の中の王道といえる問題でした。しかし、80年代の研究で「胸腺の中で自己反応性細胞は負の選択によって除かれる」が明らかになって、解決したかのように考えられていました。そのような中、世界でただ一人、もう一つの解に到達されたのです。それが「制御性T細胞による末梢レベルでの免疫寛容の誘導」です。これは生命科学における大発見であると同時に、医学的にも超重要です。この仕組みが破綻すると、自己免疫疾患が起こるのです。
私と、坂口先生との関係についても述べておきます。坂口先生が1999年に医生研の前身である再生医科学研究所に着任されました。当時私は別な研究室にいたので、直接の弟子ではないですが、親しくして頂き、免疫学について本質的な事を、直接学ぶ事ができました。私は2004年に横浜の理研にチームリーダーとして異動しましたが、その後もずっと親しくさせて頂いてました。
2010年に坂口先生は大阪大学に異動されましたが、その後も再生研(現医生研)でラボを維持されています。私は2012年に再生研の教授として京大に帰ってきましたが、それをきっかけに坂口研とはさらによく行き来をするようになり、研究についての相談などをしてきました。そのような中で、治療法の開発について、前述のように、志を一つにすることができました。それで、レグセルの立ち上げに際して、声をかけていただけたのです。
レグセルを立ち上げた後の会社の運営については、役員として会社の経営をされていた坂口先生の奥様である教子先生とも、ずっと打ち合わせを続けました。坂口先生は奥様を「同志」と表現されていますが、レグセルの立ち上げ時に関しては、末席ながら私も「同志」に加わっていたと思いますし、今もよく3人で食事に行ったりします。普段から、これからも「共闘しよう」という話をしています。
写真は本日10月10日、受賞されてから初めて京都大学の医生研に先生が来られたときにインタビューさせていただいた時のもので、近々医生研のYouTubeにてその時の模様をアップする予定です。
坂口先生、本当におめでとうございます!
リバーセル株式会社最高科学顧問
京都大学医生物学研究所 所長 教授 河本宏